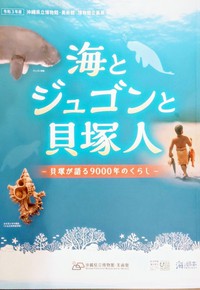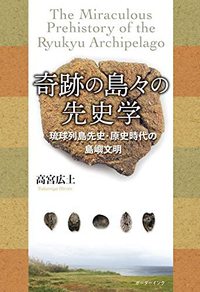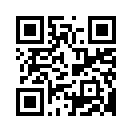2011年11月27日
第65回日本人類学会大会 その4(雑感)
国立科学博物館人類研究部長の溝口優司さんの最近の著書「アフリカで誕生した人類が日本人になるまで」
港川人や上部港川人研究の最近の動向も興味深い。
港川フィッシャーの周りのフェンスは、新しくなっているが、港川フィッシャーは十分な保護も活用もされていないのが現状。
港川フィッシャーに行くには、この門を通らなければならない。
(この門の鍵を、八重瀬町立具志頭歴史民族博物館から借りて見学できる。)
沖縄では初めての開催となった、日本人類学会大会(第65回)に一般参加しての雑感。
東北大学の百々幸雄さんの発表者に対する一刀両断の指摘に、たじろぐ発表者や答えに窮する発表者の姿が印象的だった日本人類学会。(後で折り合いが付いたかは不明)
学会会場の常設展示室の前で、「(アボリジニ風に)港川人の顔が変わりましたね。」と話しかけると、国立科学博物館人類研究部長の溝口優司さんは、「(港川人の顔が変わっても、)その価値が下がるものではありません。」と言い残すと、学会の総会へ向かわれた。
溝口さんは、最近の著書「アフリカで誕生した人類が日本人になるまで」中で、「約2万前の港川人と現代人のアボリジニが似ていても、それだけでは、どのようなつながりがあるのかわからないのです。系統の違う人が、環境への適用によって、偶然同じような形態になることもあるからです。」と述べている。(港川人の顔が変わったことに関心のある方は、下のタグの港川人の顔をクリックしてください。)
気になっていた名古屋工業大学の小田 亮さんのポスター発表「インセスト・タブー:社会契約か予防措置か?」。聞き耳を立てての話しだったが、興味をそそられた。
ポスター発表会場で、一番の賑わいを見せていたのは、慶応義塾大学の赤松 美穂さんの「現代人における頭蓋骨と脳形態の対応関係の定量化」。若手男性研究者(?)に囲まれ、話しが聞けなかった。
琉球大学の土肥直美さんは、「琉球列島の人類学:現状と課題」の発表で、「白保竿根田原洞穴遺跡の調査では、人類学者と考古学者の協働作業の成果が出ている。港川フィッシャーでは石器等が見つからないため、考古学的には受け入れられていない。そのため、港川フィッシャーは評価されず、保護も活用もされていない。(遺跡の指定がされていない)
このような現状も一般には知られていない。」
人類学者と考古学者の間のフィッシャー(割れ目)を埋めるためにも、さらなる両者の協働作業が必要だ。